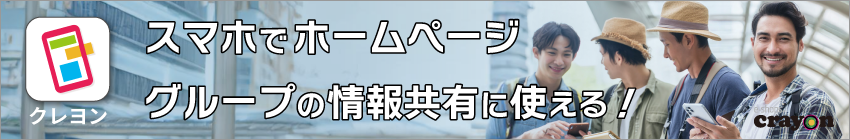
人必ず自ら侮りて然る後に人之を侮る
(ひとかならずみずからあなどりて、しかるあとにひとこれをあなどる)
何事もひと度諦めてしまうと、その人の神秘性が失われてしまうものだ。存分に生きている人は、みな美しい。その美しさは誰もが認める美しさであり、誰かの興味をかき立てたり、誰かの役に立つ美しさである。
脚力尽くる時 山更に好し
( きゃくりょくつくるとき やまさらによし )
たとえいまは意味が見えなくても、自らが選んだ道を歩き続けていく。自らの人生すべてが愛せるように。
あなたを見てわたしは驚き、拍手する。
あなたは自らの人生に驚き、また拍手する。
あなたの今日は、誰かの明日になり、わたしの今日もまた、誰かの明日になる。
辛いものは癖になります。辛いという感覚は、味蕾ではなく痛点で感じるものだからです。
私たちは苦痛を受け止めるために、脳内ホルモンを分泌し、苦痛と快楽を通底させてしまいます。
カラダ(本音)からのメッセージをアタマ(建前)がやわらかく受け止めることで、ココロ(思想信条)を支える。
私たちには、それが出来るはずなのです。
人間って、いまある現実と宗教にも似た智慧ともいうべき誤謬との間を無意識に生きる存在なのだと考えるようになりました。あと、生き方のテクネーとか魂の置き場所を知るためには教養が必要であることを再認識しました。
情と知と志の使いどころや高校生物の可能性に気づかされました。
野上は目が細い。よくぞ、彼のお母様は目を細くお産みになったものである。大工の見習いは、最初に自分用の道具箱をつくることから始まる。ある工務店の社長が言うには、不細工な仕上がりだった子ほどいい職人になることが多いそうだ。野上の観察眼の鋭さは、その細い目を見開く必要から培われたものだろう。しかし、世の中のすべてのものを批評的な視線で観察してしまうと、心身ともに疲弊してしまう。ましてや、いまの状況では身体に堪える。彼の目の細さが、ときにはこの世の中のすべてが気になって仕方ない競走馬に施されるブリンカー(遮眼帯)みたいな役割りを果たしてくれればとも思う。過去にいろいろとあった二人や二つの共同体が未来に向けて関係を修復しようとするとき、プラットフォームづくりに欠かすことが出来ないのは、薄目で相手との過去をふり返ったり相手のイヤなところを見る姿勢である。妄想とまではいかないまでも、夢を見る根性や何かを愛するための勇気を生み出すことのできる希望は大事だ。世の中、形而上の誤謬(ひょうたん)から駒が出ることもある。心から願ったことやふざけて言ったことが実現することもある。人生は楽しい。人生は残酷だ。それでも、人生が素晴らしいのはそこにある。朝が来た。ああ、一日がはじまる。まぶたを閉じ、すこし考えることをやめる。朝陽に向けて、しばし祈りを捧げるために。
https://dot.asahi.com/dot/2018061500082.html